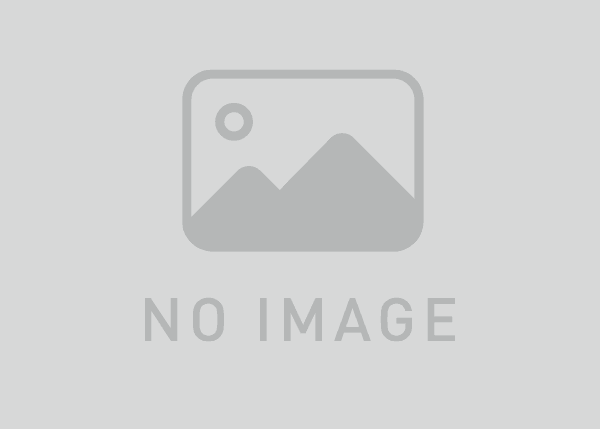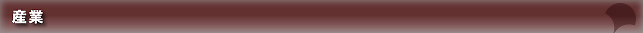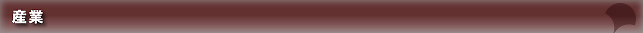
海上災害が収束するまでの全ての防除活動に関与
海上保安庁横浜機動防除基地 機動防除隊・副隊長 上田修
文字通り、仕事に自分の命を賭けることもある人たちがいる。一般の人にはなかなか知られることのない彼らの仕事内容や日々の研鑽・努力にスポットを当て、仕事への情熱を探るシリーズ。
今回は、横浜市中区の海上保安庁横浜機動防除基地に勤務する、機動防除隊の上田修副隊長。海上への油流出や火災などの海上災害が起きた場合に、迅速かつ適切な措置方法を現場で指導・助言する、海上防災のエキスパートをご紹介したい。
(取材/袴田 宜伸)
海上災害が収束するまでの全ての防除活動に関与
第三管区海上保安本部(横浜市)に機動防除隊が編成されたのは、1995年
当初は2隊8名だったが、1997年に東京湾で発生したダイヤモンドグレース号の原油流出事故などを受けて、組織を強化。1998年に横浜機動防除基地が設置され、隊員数も現在では、4隊16名となっている。
機動防除隊の職務は、海上への油流出事故や海上火災などの発生時における、油防除や消火の措置に関する技術的な指導・助言が中心となる。
法律上、海上に油が流出した場合、流出油を防除する義務は、流出させた船舶の所有者にある。従って機動防除隊は、オイルフェンスで油を包囲する、あるいは油吸着材で油を回収するなど、迅速かつ適切に流出油を取り除くための最適な措置方法を、船舶の所有者に対して現場で指導・助言するのである。
時には、隊員が自ら防除措置を実施することもあるが、そればかりではない。適切な指導・助言をするために事故状況の情報を収集。防除活動の早期終息を目指し、防除計画策定のために関係者間の調整も行う。
つまり機動防除隊は、現場の作業に関わるだけでなく、海上災害が収束するまでに必要とされる、全ての防除活動に関与するのである。
また、平時では、洋上で資機材を使用するといった訓練・研修を行うほか、海上防災知識の普及にも尽力。
排出油等防除協議会で講師を務めるほか、各地で講演会を開いたり、東南アジア諸国で教育訓練を行ったりしている。
必要とされる知識は幅広く、職務内容は奥深い
上田副隊長が機動防除隊に配属されたのは、今年の4月。
海上保安官としてのキャリアは13年におよぶが、新任研修期間としてこの3カ月は、一人前の隊員になるために必要な知識と技術を学んだ。
「海上防災の専門家集団という立場にありますから、各種資機材の取扱いや有害危険物質に関する化学の知識など、新たに覚えなければいけないことはたくさんあります。それに、専門的な知識がない方にもわかりやすく、自信をもって指導・助言するためには、根本から知っていないといけません」
上田副隊長は、現場の保安官だった時に機動防除隊と職務を共にした経験があるが、入隊してみるとその時に受けた印象とは大きく違った。
必要とされる知識は幅広く、職務内容は奥深い?日々そう感じながら、座学や訓練に励んだ。
「常に学ぶことばかりで苦労しました。でも、すべてが自分のためになることですし、海上防災に関するあらゆる知識を学ぶことができますから、とても充実しています」
早く一人前の隊員になって、海の汚染防止に貢献したい
機動防除隊の出動件数は、年間およそ20件。新任研修を終えて上田副隊長は、いよいよ現場に出動する。
「不安は多少ありますが、現場に出ないと覚えられないこともありますし、自分の指導・助言によって油を適切に防除できた時などには、今以上にやりがいを感じられるのだと思います。ですから、相手の立場になってわかりやすい言葉で指導・助言することを肝に銘じて、一つひとつの事案に関わっていきたいと思います」
続けて、今後の目標をこう話した。
「現場経験を含めてこれからも多くの知識・技術を身につけて、早く一人前の隊員になって、海の汚染防止に少しでも多く貢献していきたいです」
海上保安官だった父親の背中を見て育ち、「人の役に立ちたい」との思いから海上保安官の道に進んだ上田副隊長。身につけた技術・知識を活かし、海上防災のエキスパートとしてさらに活躍されることを期待したい。
![[プロフィール参照]](/images/20090720/12_01.jpg)
<プロフィール>
1972年、三重県生まれ。滋賀大学を卒業して民間の会社に勤務した後、海上保安官の道を志して海上保安学校に入校。卒業後、設標船や巡視船に乗り、航路哨戒や領海警備などにあたる。2009年4月から機動防除隊に配属。