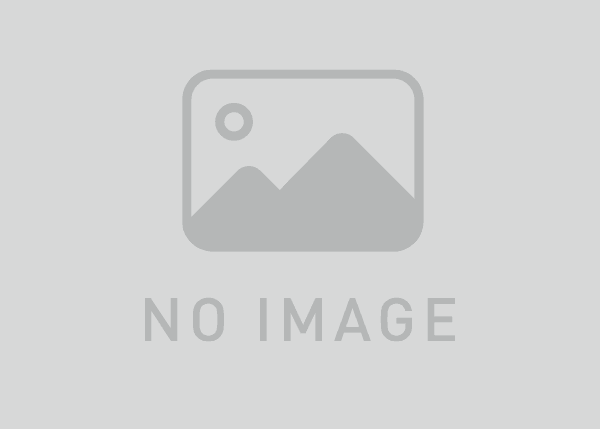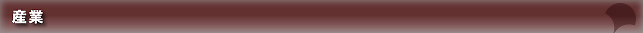
海上保安庁第三管区海上保安本部
東京海上保安部巡視艇はやかぜ・船長
大矢 俊弘
文字通り、仕事に自分の命を賭けることもある人たちがいる。一般の人にはなかなか知られることのない彼らの仕事内容や日々の研鑽・努力にスポットを当て、仕事への情熱を探るシリーズ。
今回は、江東区青海の海上保安庁東京海上保安部に勤務する、巡視艇「はやかぜ」の大矢俊弘船長。東京湾の警備、救難、海上防災、航行安全を主たる職務とするほか、船上火災の消火や荷役の立ち合いを行うなど、さまざまなシーンで活躍する船乗りをご紹介したい。
(取材/袴田 宜伸)
東京湾を舞台に日々、休むことなくパトロール

洋上を哨戒する巡視艇「はやかぜ」。18m型で乗員数は5名
第三管区海上保安本部に属する東京海上保安部には、管理課、警備救難課、交通課、航行安全課、港内交通管制室の4課1室があるほか、6隻の巡視艇と1隻の監視取締艇を駆り、救難現場などのさまざまなシーンで活躍する部署がある。それが「船艇」である。
船艇の仕事は、実に幅広い。
主な仕事は、東京湾を舞台に、工場排水による海洋汚染や法令違反の監視・取り締り、海難救助、海洋秩序の維持、海上交通の安全確保。
海を安全で美しいものとするために、洋上に出て「無検査や無資格で運行している船舶はないか」「危険物がないか」「立入禁止区域に人が立ち入ってないか」と日々、休むことなくパトロールしているほか、銃器や薬物の密輸を未然に防ぐために、警視庁や東京税関と合同で船内検索をしたり、海上に油が流出した際には、東京都港湾局とともに防除にあたったりもする。

船内浸水を想定した排水訓練の様子
はやかぜの大矢船長は、思い出深い出来事としてこう振り返る。
さらに、洋上で火災が発生した場合には、消火にも従事。東京消防庁と連携して消火することも多いが、2007年に羽田空港の北側で船上火災が起きた際には、いち早く現場に駆けつけ、巡視艇「はやかぜ」1隻で初期消火にあたった。
「はやかぜは汎用型の巡視艇ではありませんので、放水銃がなく、防火服や空気ボンベもない中での消火作業となりましたが、風上に回って火や有毒ガスから身を守るなどして、人命を失うことなく安全に消火することができました」
陸上での仕事も多く、幅広い知識が必要
また、仕事場は海上ばかりではない。
陸上での仕事も多く、たとえば放射性物質の荷役がある時には、適切に安全に荷役が行われているかを確認するためにその場に立ち会い、事件・事故が起きた際には、被疑者の取り調べや各種の書類作成も行う。
「船艇とはいえ、船に乗ることだけが仕事ではありません。いろいろな職務に携わりますから、幅広い知識が必要とされます」
このように多岐にわたる船艇の職務。
言わば、オールマイティな海の警察官であり消防官と言えるが、さまざまな職務を一つひとつ遂行していく中で大矢船長は、「幅広い目で物事を見ること」を大切にしている。
「一つの事件や事故に集中し、それだけに全力を傾けて取り組んでしまうと、周りに目が向かず、新たな事件・事故に巻き込まれる恐れがあります。事件や事故は同時にいくつも起きることがありますから、常に周囲に目を配り、安全に配慮しながら処理するように心がけています」
現状に甘んじることなく日々精進していく

停泊中のはやかぜ。東京海上保安部の巡視艇は、ほかに20m型の「ゆめかぜ」「ゆりかぜ」「いそぎく」「やまぶき」と、35m型の「まつなみ」がある。
職務上、人の命を預かることもある。そのため、神経を使うことも少なくないが、それだけに得られる達成感は大きい。
「溺れている人などを無事に助けることができた時や、救助された人が感謝していたと人づてにでも聞いた時には嬉しく思います。それと、仕事を終えた後にみんなで飲むお酒は格別です」
そう言って笑顔を見せた大矢船長。最後に今後の目標を聞いた。
「救難の資器材はどんどん進歩していますし、テロも複雑化しています。そのため、学ばなければいけないことは多くありますから、現状に甘んじることなくこれからも日々精進して、自分のできることを一つひとつしていきたいです。そして、できるだけ長く船に乗っていられればと思っています」
一を習えて十を知り、十から帰る元のその一?大矢船長は、最後にそう続けた。
自分が歩んでいる道は、果てしなく続く無限回廊のようなもの。つらく厳しいが、大矢船長は、そこにやりがいをも感じながら前を見据え、確かな足取りで歩み続けていく。
![[プロフィール参照]](/images/201001/12_01.jpg)
<プロフィール>
1965年、埼玉県生まれ。高校卒業後、海上保安学校に入校。卒業後、本庁の測量船や千葉海上保安部の消防船、プルトニウム輸送の護衛船である「しきしま」などに乗り、2007年の4月から現職に就く